現代の体を動かすヨガには、大きな意味では、ハタヨガに分類されます。
いろんな流派がありますが、基本的にはハタヨガの流れにある。
ヨガを学ぶうえで、もっとも有名で権威のあるヨガの教えというと聖者パタンジャリ師がまとめたとされるヨーガ・スートラでしょう。

ハタヨガを学んでいると当たり前のようにヨーガ・スートラをティーチャートレーニングなどで、ヨガのバイブルとして使われていますが、その違いがとても自分は面白いと思っています。ヨガ哲学を学んでいくなかで、この異なる2つの世界観、宇宙の捉え方に自分はヨガの世界の深さを感じてしまい、どんどんのめりこんでいき、今も学びを継続しています。 知識をアップデートするたびに、今までの知識とまた違うことが出てきたり、他の学びとの関連やつながりが考察できたりします。
日本語でもヨーガ・スートラの解説本がたくさん出ていて、私も何冊も持っています。
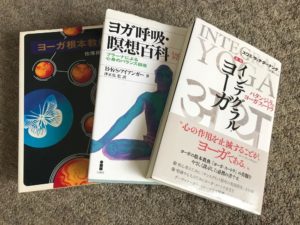
ヨーガ・スートラは、4000年前に書かれたなんて説もありますが、西暦5世紀前後ころに纏められたという説が有力で、ヨーガ・スートラのもととなった思想は、ヴェーダ哲学のひとつのサンキーヤ学派で、サンキーヤ哲学にヨガの実践をするようにしたのがヨーガ・スートラで、ヨーガ学派と言われています。
現代ではパタンジャリのヨーガ・スートラ=ラージャ・ヨーガと理解されています。ラージャ・ヨーガとは瞑想のヨガ、王様のヨガといわれ、ヨーガの実践のひとつです。
ただヨーガ・スートラの中ではラージャ・ヨーガという言葉は出てきません。これは後の世でくっつけた後付けであった可能性や、ラージャ・ヨーガの経典の一つで残ったのがヨーガ・スートラだったのかもしれません。ハタヨーガの教典のハタヨーガ・プラディーピカーでは、ラージャ・ヨーガとは、サマディ(三昧)のことをいいます。
ヨーガ・スートラといえばもっとも有名なのは、1章の2の
YOGAS CHITTA VRITTI NIRODHAH(ヨーガ チッタ ブリッティ ニローダハ)
ヨーガ・スートラの世界観 二元論
ヨーガ・スートラを理解する上で、大事なのは、その世界観だと思います。 ヨガ・スートラの宇宙観はサーンキャ哲学の二元論がベースになっており、世界をプルシャとプラクリティの2つに分類しました。
プルシャとは、精神原理、真我。
観るもの。 プラクリティは、物質原理、肉体や心、観られるもの。 世界はプルシャとプラクリティの2つで、プラクリティから、さまざまなものが生まれて派生しているが、私たちの本質は観るものであるプルシャであり、ヨーガの修行は自分の本質であるプルシャであるということに気づくことであるってのが、ヨーガ・スートラの世界観。
ハタヨーガの世界観は、不二一元論
一方でハタヨガの世界観は、ハタヨガは仏教密教とヒンズー教シヴァ派から生まれたナータ派の修行法で、タントラ思想があります。
タントラ思想は、ヴェーダ哲学のヴェーダーンタ哲学とインドの土着の信仰が融合したものです。
ヴェーダーンタ哲学は不二一元論で世界はたった一つのブラフマン(宇宙の根本原理)のみであるという考えがある。ヨーガ・スートラが心の修行法とすれば、タントラは身体の鍛錬に重きを置いています。
男性性と女性性の統合など陰陽相反するものを合一、一つにする。 アーサナや浄化法など身体の訓練や、クンダリーニやチャクラといった目に見えないエネルギーをコントロールすることで、心身の合一により覚醒に至るといったより神秘的な要素が強くなります。
タントラ思想はチベット仏教や、日本の仏教の真言宗などにもある。 インドの土着の信仰には男性器崇拝(リンガ崇拝)などがあるが、これも日本やアジア各地などに今も残っている。
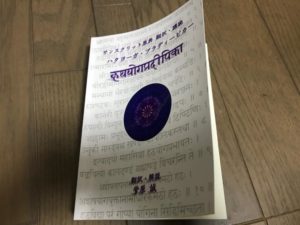
ハタヨガは、ハタヨーガ・プラティピカーによるとラージャ・ヨーガへの梯子であるとされているが、ヨーガ・スートラと関係があるかは、記述はなく、ここでのラージャヨーガは、サマディのことをいう。
聖なるアーディーナータに礼拝あれ;彼によって説かれたハタヨーガの学術は、至高のラージャ・ヨーガを登らんと欲する物を梯子のように、輝き導く。 ハタヨーガ・プラティピカーの1−3
ハタヨガで大事なのは、太陽(ハ)と月(タ)、男性性(シヴァ)と女性性(シャンクティ)の3つの相反するエネルギーをコントロールしようとすることではないだろうか。
肉体やエゴを持つ人間が宇宙意識と一つになり、解脱、解放を目指そうとしたと考える。 ラージャ・ヨガとハタヨガの世界観の違いには、インドの古くからのカーストだったりとさまざまなものと関係していると考えられる。
ラージャ・ヨーガはバラモンの修行の方法が中心だったとされ、ハタヨーガは、もっと底辺というのか一般というのか表現が難しいが、出家していない人たちの修行であったようで、そこには仏教の影響もある。 ヒンズーと融合しながら密教化していった仏教のタントラから、ハタヨガが生まれたことでもインドの宇宙感の表現であったのだろう。ヨーガ・スートラのヤマ、ニヤマなども仏教やジャイナ教などとの共通する教えがあり、歴史の中で影響しあっていたのだろう。
ヨーガスートラでは、イーシュヴァラという神に祈念する。この神は人格化した神ではなく、世界の根源的な存在といえる。一方でハタヨーガはシヴァ派から生まれたことでわかるようにシヴァ神を信奉しておりシヴァとシャンクティの合一を目指す。
ヨーガ・スートラとハタヨーガの違いと本質は?
ヨーガ・スートラでは瞑想することによって、少しずつエゴや私という意識を落としていって、世界を純粋に観る力とつけていくのと、ハタヨーガは、アーサナやプラーナヤマにより体に意識を向けて体や呼吸をコントロールすることで、自分の本質が肉体や心という物質ではなく、精神的なものであるという本質に気づいていくということだと理解しています。
現在の主流はヴェーダンタ哲学の不二一元論であり、サーンキヤ哲学の二元論については疑問が多々あると思いますが、ヨーガ・スートラの中には現代に生きるうえでもとても大切な教えで溢れていて、役立つと思います。
この記事を読んで、ヨガ哲学に興味を持ってくれる人がいたら嬉しいなと思います。
パタンジャリのヨーガ・スートラを学ぶ 1章1節 Atha アタ
パタンジャリのヨーガスートラを読む 1章5節ー6節 ヴリッティ(心の作用)
ハタヨーガの開祖が示す教典 ゴーラクシャ・シャタカ サンスクリット語全解について
ヨガのアーサナの本当の意味とは? アーサナとは神様と繋がること?
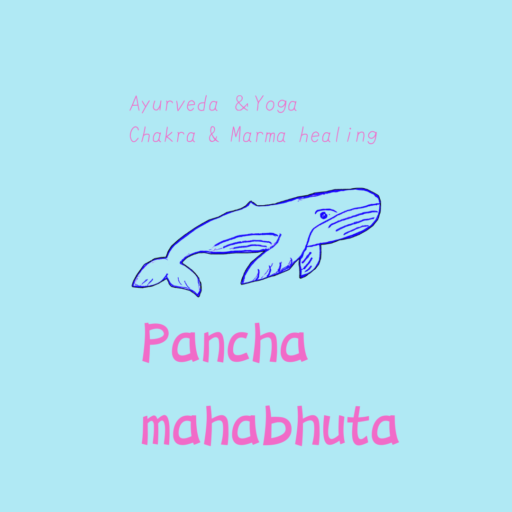
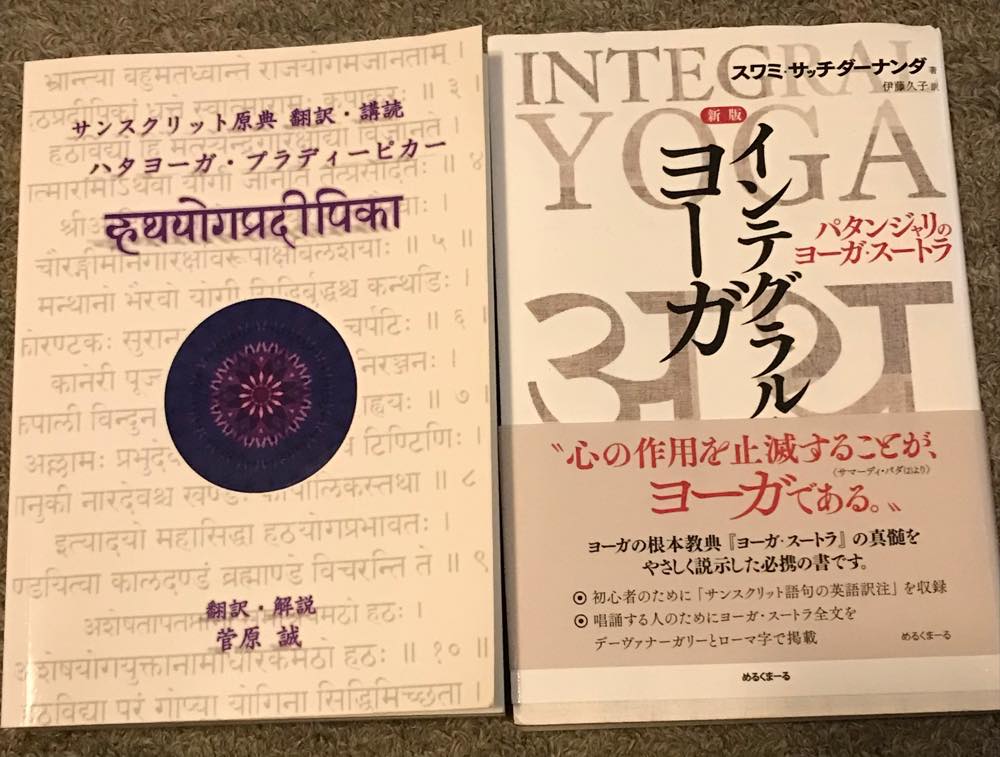



コメント
[…] 知ってる?ヨーガ・スートラのヨガとハタヨガの違い […]